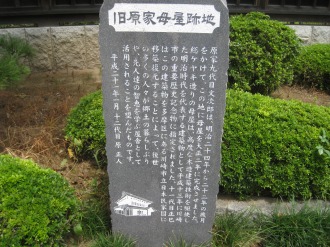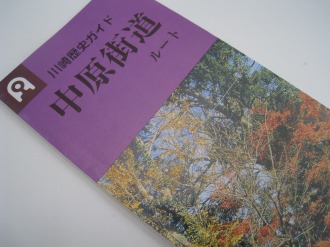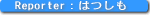
財団法人川崎市文化財団の事業に
「川崎歴史ガイド」というものが
あります。これは、
市内の歴史文化遺産の保存と紹介を目的とした
事業で、市内の歴史をたどる
9つのルートを設定し、現地に
ガイド
パネルを設置するほか、パンフレットを作成しているものです。
■川崎市文化財団 歴史ガイド
http://homepage2.nifty.com/k-bunkazaidan/guide/index.htm
■川崎歴史ガイドのパンフレット
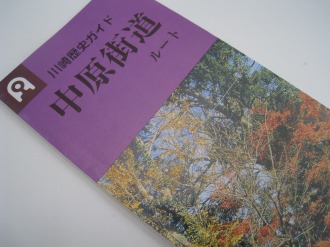
中原区においては、
「中原街道」と
「二ヶ領用水」がルートに設定
されており、そのうち「中原街道ルート」についてはガイドパネルが
設置されています。
■川崎歴史ガイドのガイドパネル

そのうち
「中原街道のカギ道」については
2008/8/8エントリですでに
取り上げておりますが、今回より
「中原街道ルート」の全体を不定期
連載で巡っていきたいと思います。
というわけで、今回はスタート地点の
「丸子の渡し」からですが、
その前に
中原街道について少々。
■現代の中原街道(武蔵中原駅付近)

中原街道は、
江戸と平塚の中原を結ぶ街道で、おおよそ中世には
成立していたようです。中原区では意外に思う方もいらっしゃる
かもしれませんが、
「中原街道」という名前は平塚の中原が由来と
なっています。
平塚の中原には徳川家の別荘
「中原御殿」がありました。これは
徳川家康の命により
1596年に建てられたもので、
1608年に2代将軍
秀忠が仮御殿として建てた(その後増改築)
「小杉御殿」に先立って
成立しています。
江戸自体初期までは
東海道が整備されておらず、徳川家康、秀忠、
家光の3代にわたって主要街道として利用されていました。その後
東海道にその立場を譲り、かつての繁栄を失うことになりますが、
その後も沿道の生活物資や農産物を運ぶ街道として利用され、
現在に至っています。
そのような歴史ある街道であるため、
現在でも街道沿いには旧家や
古くからの商家、石碑などが残り、地名にも当時の名残が見受けら
れ、「川崎歴史ガイド」のガイドパネルが設置されています。
さて、スタート地点の
「丸子の渡し」ですが・・・、
■丸子の渡し(丸子橋)

いきなりですが、
ガイドパネルがありません。川崎市文化財団の
ウェブサイトにも記載されていますが、
行方不明になっている
ようです。
それなりの大きさで、金属製ですので重いと思うのですが、ガイド
パネルは自分で歩きませんので、
どなたかが持ち去ってしまった
ものと思います。使い道はわかりませんが・・・。
・・・気を取り直して「丸子の渡し」ですが、丸子橋ができたのは
それほど大昔のことではありませんで、
1935年のことです。
それまで、中原街道を利用する方は
渡し舟で多摩川を渡っていた
もので、それが「丸子の渡し」と呼ばれていました。
当時は多摩川の堤防の内側まで集落が広がっており、渡し場付近
には
「松原」、東横線の鉄橋から上流には
「青木根」と呼ばれる集落
がありました。集落では農業のほか、多摩川の砂利取りや川舟作り
などをして生計を立てていました。
商店も営まれたほか神社なども集落内に祀られ、渡し場周辺は
人々
の生活の場であったようです。
■「青木根集落」のあった東横線上流

しかし、その丸子の渡しと集落もなくなる日がやってきます。
1921年頃から始められた
多摩川の築堤工事により、青木根・松原は
移住を余儀なくされます。
「川崎歴史ガイド」ですと自然消滅したかのようにぼかした記述に
なっていますが、実際には代替地の補償もない強権的な移住だった
ようです。
青木根には
天満宮がありましたが、移住に伴って一旦
丸子山王日枝
神社に合祀され、その後あらためて
上丸子天神町に移されました。
天満宮は
天神さまとも呼ばれますが、それが
上丸子天神町の地名の
由来となっています。
上丸子天神町は多摩川沿い、青木根の付近にあたりますが、
青木根
から多くの方が上丸子天神町に移住したそうです。
そして、前述の通り
1935年に丸子橋が完成したことで「丸子の渡し」
も完全に役割を終え、松原・青木根集落に続いて姿を消すことと
なりました。
現在の河川敷には当時の名残は(ガイドパネルも)ありませんが、
2007年より「中原街道時代まつり」の一環として「丸子の渡し」が
復活しています。
■二ヶ領せせらぎ館 丸子の渡し復活
http://www.seseragikan.com/ivetokiroku/090718watasi/index.html
現在の丸子橋については
2009/7/2エントリでご紹介した通りなの
ですが、この橋ができるまでにさまざまな歴史があったわけですね。
今回は以上です。
次回日時は未定ですが、ぼちぼち
武蔵中原駅までの街道筋を辿って
いきたいと思います。
■「丸子の渡し」周辺マップ

【関連リンク】
2008/8/8エントリ 中原街道のカギ道(前編) 小杉御殿と西明寺
2009/7/2エントリ 丸子橋で、都県境に立つ